2025年3月14日
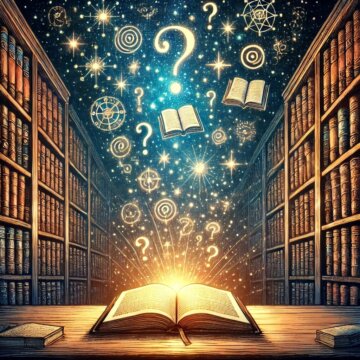
なぜ私たちは真実を求めるのか?
私たちは日々、真実を追い求めている。ニュースをチェックし、デマを疑い、SNSで拡散される情報の真偽を確かめる。子どもの頃には「どうして空は青いの?」と質問し、大人になると「このニュース、本当なのか?」と考えるようになる。
だが、ここで立ち止まってみよう。
私たちは本当に「真実そのもの」を求めているのか? それとも、単に「信じたいもの」を探しているだけなのか?
この問いに真正面から向き合ったのが、19世紀の哲学者フリードリヒ・ニーチェだった。彼は、人間が真実を求めるのは「それが善だから」ではなく、「そうしなければならないという思い込みがあるからだ」と指摘する。
しかし、そう言われると不安になる。
もし、真実を求める理由が単なる思い込みだったとしたら?
真実は生存に必要なのか?
たしかに、私たちは「真実を知ることが生存に役立つ」と考えがちだ。毒キノコと食用キノコの違いを知らなければ、命を落とすかもしれない。狩猟採集時代に「この果実は安全か?」という問いに正しく答えられた者が生き延び、現代の私たちがいる。
しかし、ここで少し寄り道をしよう。
真実を知ることは、いつも生存に役立つのか? たとえば、『マトリックス』という映画を思い出してみてほしい。この作品では、人間たちは機械に支配され、仮想現実の中で生きている。しかし、ほとんどの人はそのことに気づかず、普通の人生を送っている。もし彼らが「真実」を知ったらどうなるか? それは幸福につながるのか、それとも苦しみを生むのか?
これは単なる映画の話ではない。私たち自身も、時に「知らないほうが幸せ」なことがある。たとえば、長年信じていた価値観が根本から覆されたとき、そのショックは計り知れない。だからこそ、人は時に「見たいものだけを見る」という選択をする。
ならば、こう考えてみよう。
私たちが求めているのは「真実そのもの」ではなく、「生きるために都合の良い真実」なのではないか?
フィクションと真実 なぜ嘘に心を動かされるのか?
ここで、もう一つ別の視点を入れてみよう。
もし「真実こそが最も価値あるもの」なら、なぜ私たちはフィクションにこれほど惹かれるのだろうか?
たとえば、小説や映画は「作り話」だ。それにもかかわらず、私たちはそれに涙し、感動し、時には人生観さえ変えてしまうほどの影響を受ける。
ここで、村上春樹の小説『ノルウェイの森』を例に考えてみたい。この物語は完全なフィクションだが、読んだ人の多くは「この物語には真実がある」と感じる。なぜだろう? おそらく、それは「事実としての真実」ではなく、「人間の感情に深く根ざした真実」がそこにあるからだ。
このことから、次のような仮説が導き出せる。
私たちは「事実としての真実」ではなく、「意味のある真実」を求めているのではないか? それがたとえ虚構の中にあったとしても。
真実を求める意志、それは権力の意志か?
さて、ここでもう一つの視点を加えてみよう。ニーチェは、「真実を求める意志」は「権力を求める意志」ではないかと考えた。つまり、私たちは単なる知的好奇心からではなく、「より強く、より優位に立つために」真実を求めているのではないか?
たとえば、科学の発展を考えてみよう。私たちは純粋な知識欲だけで科学を発展させているのだろうか? それとも、「生存競争に勝つための手段」として科学を求めているのか?
歴史を振り返ると、「知ること」は常に「支配すること」と結びついてきた。産業革命、インターネット、人工知能——これらはすべて、「より多くを知る者」が「より強い力を持つ」ことを証明している。
では、ここで問い直してみよう。
私たちが真実を求めるのは、純粋な知的探究心なのか? それとも、「生き残るための武器」としての真実なのか?
それでも、なぜ真実を求めるのか?
ここまで考えてきたように、私たちが求めているのは必ずしも「絶対的な真実」ではない。むしろ、「生存に役立つ真実」や「意味のある真実」に惹かれる傾向があるようだ。
それならば、「真実など求める必要はない」と結論づけるべきだろうか?
いや、そう簡単にはいかない。なぜなら、私たちは「問い続けること」そのものに価値を感じる存在だからだ。宇宙の起源、意識の仕組み、死後の世界——こうした問いは直接的な生存とは関係がない。それでも人類は数千年にわたって考え続けてきた。
もしかすると、それこそが「人間らしさ」なのかもしれない。生き残るためではなく、知ることそのものに意味を見出す。
だからこそ、問い続けよう。
「なぜ真実を求めるのか?」
この問い自体が、すでに私たちが真実を求めずにはいられない存在であることを示しているのだから。
