2025年10月5日
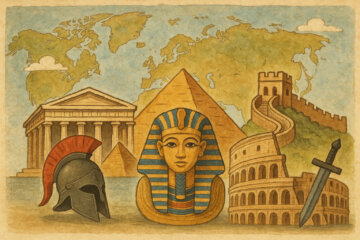
民族自決って本当に“平等”だったの?~レーニンとウィルソンの思惑を読み解く~
はい、みなさんこんにちは!今日は「民族自決」っていう、なんだか正義っぽく聞こえる言葉の、ちょっと裏側を一緒に見ていきましょう。
まず基本から。「民族自決」っていうのは、簡単に言えば「自分たちの国は自分たちで決めるよ!」っていう考え方。これが国際政治で本格的に登場するのが、第一次世界大戦の終盤です。
レーニン、聞いたことありますよね?ロシア革命を起こしたあの人です。彼が1917年に「平和に関する布告」っていうのを出して、「すべての民族に国家を決める権利がある!」と叫ぶわけです。ここで大事なのは、これは社会主義的な観点からの民族解放。帝国主義に反対するための理論武装でもあったんです。
で、その翌年にウィルソン大統領が出したのが「十四か条の平和原則」。ここにも民族自決が登場しますが、こっちはリベラルな国際秩序をつくるための方策。つまり、レーニンとウィルソンでは、同じ言葉でも背景が違うってこと!
さて、戦後どうなったかというと、オーストリア=ハンガリー帝国が崩れて、チェコスロヴァキアとかユーゴスラヴィアとかができました。これ、表向きは「民族自決の成果!」って感じですが、実は多民族国家なんですよ。特にチェコスロヴァキアはズデーテン地方にドイツ系住民もいて、後に問題になりますよね。
さらに重要なのが中東。オスマン帝国の旧領は、民族自決どころか英仏の利権争いの舞台になりました。サイクス・ピコ協定、バルフォア宣言……この辺りも覚えておきましょう。イラクとかシリアとか、線引きはまさに「大人の事情」。民族や宗教の実態?そんなの関係ない!
そしてもう一つ。民族自決って、実は白人のための自決だったんじゃないの?って話です。アジアやアフリカの植民地には一切適用されませんでした。日本が提案した「人種平等条項」が退けられたのも象徴的ですよね。
では最後に確認。民族自決は理想ではあったけど、現実は極めて政治的に使われた。誰がその「自決」を認められて、誰が除外されたのか。それを見抜く視点を、君たちには持っていてほしい。
はい、今回はここまで。
