2025年8月24日
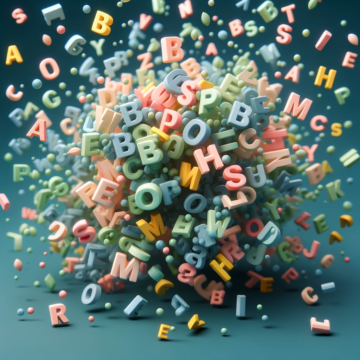
〜想像力を育てる“仮定法過去”の話〜
英語を教えていて、生徒からたまに聞かれるんです。
「先生、“仮定法”ってなんであるんですか? めっちゃ面倒じゃないですか」って(笑)
たしかにその気持ち、よくわかります。
僕自身、学生時代は「なんで“今の話”なのに“過去形”使うの?」って、ずっとモヤモヤしてました。
でも、教える立場になって気づいたんです。
この文法、ただのルールじゃなくて、想像力の練習なんだなって。
「もし〜なら、〜するのに」って思ったこと、ありますよね?
たとえば――
「もっと時間があればな〜」
「彼女が今ここにいればいいのに」
これってどれも、“今とは違う世界”を頭の中で描いてる。
英語では、こんな「現実とは違う想像の世界」を言葉にするために、仮定法過去というちょっと特別な文法を使います。
仮定法過去の基本のカタチとは?
英語の仮定法過去は、2つのパートからできています。
if節(仮定の部分):もし〜なら
主節(その結果):〜するのに
この2つを組み合わせて、「現実とは違うけど、もしそうだったら…」という場面を表現します。
文の基本構造は、次のようになります。
If + 主語 + 動詞の過去形, 主語 + would / could / might + 動詞の原形
この形を覚えておくと、仮定法過去の文がスムーズに作れるようになりますよ。
実際の例を見てみましょう
If I had more time, I would read more books.
(もしもっと時間があれば、本をもっと読むのに)
→ つまり、「時間ないんだよな〜」っていう現実を前提にした、空想のひと言です。
If she were here, we could start the meeting.
(もし彼女がここにいれば、会議を始められるのに)
→ 「彼女、今いない」っていう現実をベースに、理想の状況をイメージしてるんですね。
なぜ“過去形”なのに“今の話”なのか?
この部分、最初にひっかかる人が多いんです。
でも実は英語って、「現実と違う話をするときは、あえて“過去形”を使う」というルールがあるんです。
ちょっと不思議ですよね。
でも、過去形を使うことで、「これは現実の話じゃないよ」というサインになる。
英語って、そうやって文法で“心の距離”まで表すんです。
