2025年5月9日
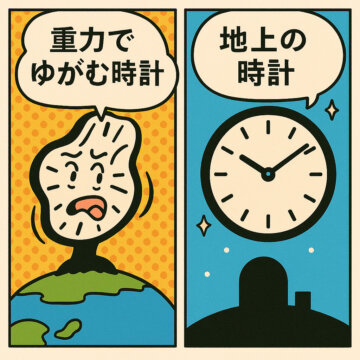
スマートフォンで地図アプリを開けば、自分の現在地が一瞬で表示されます。あまりにも当たり前になっていますが、その裏には、20世紀に登場した物理の大理論――アインシュタインの「相対性理論」が深く関わっているのです。
グーグルマップが使うGPSは、地球の周囲を回る人工衛星からの信号を使って位置を割り出しています。その精度を保つためには、衛星に積まれた超高精度の時計の時刻と、地上の時計の時刻がピッタリ合っていなければなりません。ところが、実際にはその“ピッタリ”が難しい。なぜなら、相対性理論によれば、時間の進み方は場所や速度によってわずかに変わってしまうからです。
ちょっと不思議に感じるかもしれません。そこで、こう考えてみてください。
重力のある場所では、時間が少しだけゆっくり進む。この現象をわかりやすく例えるなら、逆方向に動いているエスカレーターを駆け上がっている人のようなものです。普通に走れば前に進めるはずなのに、エスカレーターが下に動いているせいで、その力が打ち消され、なかなか進めません。これと同じように、重力の強い場所では「時間そのものが前に進みにくくなる」のです。
さらに、もうひとつ。人工衛星は秒速4キロメートル近いスピードで地球の周りを回っています。これだけのスピードでも、時計の進み方はほんのわずかに遅くなります。つまり、GPS衛星の時計と、地上の時計では、毎日少しずつズレていってしまうのです。そのままにしておくと、1日で10キロ以上も位置がずれてしまいます。
このズレを補正するには、相対性理論を使って計算するしかありません。実際、GPSの設計にはこの理論が組み込まれており、補正なしでは今の正確な位置情報サービスは成立しません。
そしてこれは、単なる理論ではありません。NASAの観測では、地球から2万9千光年も離れた星のペアから出た光が、予測通り赤い波長にずれているのが確認されました。これは「重力赤方偏移」と呼ばれ、重力が光にも影響を与える証拠です。そんな壮大な現象が、スマートフォンの中で静かに応用されている――ちょっと面白いと思いませんか?
科学は時に難しく思えます。でも、それがこうして日々の暮らしの中で実際に役立っていると知ると、ぐっと身近に感じられるのではないでしょうか。
