2025年9月25日
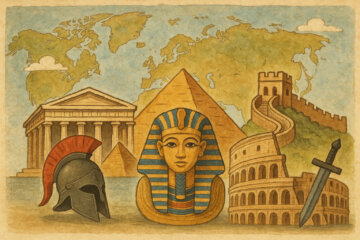
帝国が崩れたとき、何が残った?― 国境と民族の“その後”を考える
「帝国の崩壊」と聞くと、壮大な歴史の終わりを連想するかもしれません。でも本当に大切なのは、そこから始まった“新しい国づくり”のプロセスです。そして、その形は国によってまったく異なっていました。
たとえば、第一次世界大戦で敗れたオーストリア=ハンガリー帝国は、多くの民族を抱えていたがゆえにバラバラになります。オーストリアはドイツ語圏に縮小され、ハンガリー、チェコスロヴァキア、ユーゴスラヴィアなどが独立。ただし、これらの新国家もまた多民族国家であり、「民族ごとの独立」とは一概に言えません。国境と民族の境界は、理想通りには引けなかったのです。
一方で、オスマン帝国は崩壊後、ムスタファ・ケマル(アタテュルク)が主導する近代化革命によって、トルコ民族を中心とした国民国家を目指します。1923年に誕生したトルコ共和国は、多民族的な帝国の遺産を整理し、「トルコ人によるトルコ国家」を打ち出しました。
清朝の崩壊後に成立した中華民国は、「五族共和」を掲げ、漢族・満州族・モンゴル族・チベット族・ウイグル族の共存を理想としましたが、現実には漢族中心の体制となり、周辺民族との摩擦も絶えませんでした。
ロシア帝国の崩壊後に登場したソビエト連邦も、多民族国家を継続する道を選びます。表向きは「民族の平等と自決」をうたっていたものの、スターリン時代には強制移住や弾圧が行われ、理想と現実の差は大きなものとなりました。
このように、帝国崩壊後の国家形成には「民族国家化を進めた例」と「多民族国家を再構築しようとした例」がありました。しかし、そのどちらの道も、単純ではなかったのです。
現代でもこのテーマは終わっていません。ウクライナ情勢やカタルーニャの独立運動など、国家と民族の関係は揺れ続けています。だからこそ、帝国が崩れたとき、どんな選択がされ、何が失われ、何が続いてきたのかを知ることには、大きな意味があるのです。
