2025年9月18日
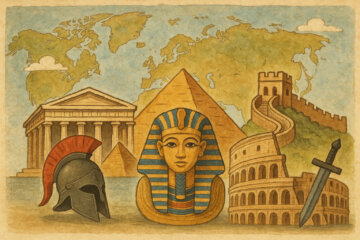
穀物法廃止の裏側に何があった?――自由貿易とイギリスの国益を読み解く
「自由貿易」という言葉には、どこか理想主義的な響きがあります。しかし、19世紀のイギリスがこの原則を選び取った背景には、はるかに現実的で計算された国益が横たわっていました。その象徴が、1846年の穀物法廃止です。
この法律は、ナポレオン戦争終結後の1815年に導入されたもので、安価な外国産穀物の流入を制限し、地主たちの利益を守るものでした。戦時中に高騰していた穀物価格が平時に下落し、農業経済が打撃を受けた中で、政治を握っていた地主層が押し通したのです。しかし、その影響で都市の労働者は高い食料価格に苦しみ、製造業者も賃金上昇を懸念して撤廃を求める声を上げ始めます。
こうした動きを組織的に展開したのが、「反穀物法同盟」でした。彼らは講演や出版、請願活動を通じて世論を動かし、政治に揺さぶりをかけていきます。さらに追い討ちをかけたのが、1845年に始まるアイルランドのジャガイモ飢饉。これは人道的危機であると同時に、イギリス政府にとって政治的な試練でもありました。
最終的に穀物法を廃止した首相ピールは、党内の反発を受けて退陣することになります。それほどまでにこの政策転換は、社会の利害対立を鋭く反映したものでした。
自由貿易への転換は、道徳的な理念ではなく、工業国として世界市場を掌握しようとするイギリスの現実的な戦略だった――こう捉えると、歴史の風景が少し変わって見えるかもしれません。今日の国際関係を見渡しても、米中の貿易摩擦や経済連携協定の交渉など、国家はいつの時代も「理想」と「現実」のあいだで舵を切っています。
歴史は過去の記録であると同時に、現代を読むためのレンズでもあるのです。
